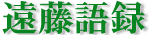

| ||||||||||||
| 雨にぬれる | ||||||||||||
|
雨にうたれたり、水にぬれることは、ひどく恐れられる。体温を奪われて、からだが冷え、胃腸をこわしたり、カゼをひいたり、ともすると肺炎やリウマチになったりするからで、からだ中がぐっしょり濡れるのはもとより、靴下がぬれるだけでも、やられるものもある。 年60余。温疫(流行性熱病)、舌胎(苔)黒、絶食数日。十死不治の証なり。余(予)一診の上、薬三貼を投じて去る。此夕は、実に文化3年丙寅の祝融(火事)なりければ、病人を伴ひ遁れんとするうち、早くも近隣まで延焼に及びたれば、是非なく病人を、夜着のまま戸板に載せ、あたりの川の上りへ、雑具を持出したる間へ置く。そのうち、ここも亦、火煙の中となりければ、已むことをえず、所詮死ぬ物として、挙家みな遁去りたり。さて病人は、始終夢中なりしが、夜半に至り、潮来って衣服を沾すに漸く心つき、段々と正気になり、そのうち潮も大分飲みたるよし。遂に、服薬せずして全快に及べり。とあり、小川顕道の養生嚢には、 医説に、陽症の傷寒(熱のたかいチフス)を煩ふもの、夜、池水の辺に伏し、水草に身をまとうて治せしむ、とあり。また、 熱症の解くべからざるもの、新に汲める水に衣裳を浸し伏せるを妙とする、と霖夢弼もいへり。などとある。 湿被包法は、西欧では古くから行われていたらしい。 近代における復活は、グレーフェンベルグの農夫、ビンセンツ・プリースニッツが応用して、種々の卓効をあげたことから。 それは、ビスマークの医シュウエンゲルが、 「非凡な医家は、湿れた手拭で、凡医が全薬局を以てするよりも多くの病人を健康にすることが出来よう」といっている通りだ。 これら湿布や水漬では、はじめ体温がうばわれるが、ついで代謝がたかまり、体温を発生し、反応的に皮膚は充血、機能をたかめ(発汗)抵抗力をますこととなる。 したがって、これらが効くか否かは、それにたいする反応のいかんによるのであって、十分な反応力がなければ、効力はないだけでなく、場合によっては、却って有害、体力・抵抗力をよわめる結果ともなる。 雨にうたれ、水にぬれてカゼをひき、肺炎になり、リウマチをおこすのは、つまり、それらの刺戟と反応力とのバランスの不調和のため。だから、体力さえ十分ならば、ミゾレや氷の流れといった冷たい水にぬれ、からだ中が冷えきってしまうのはともかく、ただの雨にぬれ、水につかるだけくらいのことは、少しもさわるものではない、どころか、むしろよい鍛錬法にもなる。 昔の人が、ながい間水につかっていて熱病が治ったというのは、熱病にはかかっていたが、もともと体質的にはすぐれていたことを示すものだし、今時の人が、僅かの雨にたたかれるだけでカゼをひいたり、リウマチになったりするのは、昔の人に比べ、体質的に劣弱で、反応性、抵抗力が十分でないことを物語るといっても、まず、まちがいはあるまい。 (48・5)
| ||||||||||||
|
<1984・4 健康と青汁 第332号より> | ||||||||||||
|
ご意見・ご要望はこちらへ | ||||||||||||
| ||||||||||||

| ||||||||||||